「●死刑制度」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3599】 前田 朗 『500冊の死刑―死刑廃止再入門』
「●ちくま新書」の インデックッスへ
死刑というものを哲学的観点から考察。死刑論議の入門書として良い。

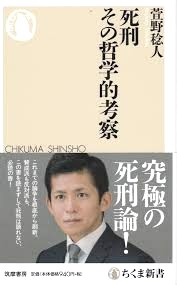
『死刑 その哲学的考察 (ちくま新書)』['17年]
本書は、タイトル通り、また本文にも「死刑をめぐる考察は必然的に哲学な考察にならざるをえない。本書の目的は、その死刑を哲学的に考察することにある」とあるように、死刑という制度を哲学的に考察したものですが、狭義の哲学に留まらず、死刑という制度を文化、道徳、法理論、感情など多面的に考察しています。
第1章では、日本が死刑制度を存置していることについて海外から批判がある一方、日本には「死んでお詫びをする」という罪悪を巡る文化的背景もあるが、そもそも死刑について、文化相対主義と普遍主義のどちらで考えるのかを考察しています。文化相対主義とは、「それぞれの文化が異なる以上、あらゆる文化に適応される"絶対的な正しさ"はないとする考え」で、普遍主義とは「あらゆる文化を超えて成り立つ正義は存在するし、存在するべきであるという考え方」を指します。そして、著者は、文化相対主義で片付けることは「それぞれの文化ですので、これ以上話すことはありません」と話が平行線のまま打ち切る形となってしまい、死刑という問題は「普遍主義」に立って考察していかなくてはいけないとしています。
第2章では、池田小学校児童殺害事件のように、死刑になるために実行される凶悪犯罪があることから、死刑制度の限界について考察します。いわば死刑の悪用という厄介な問題です。こうした事件の犯人にとっては、死刑制度は自らの欲望を叶えるために役立ったに過ぎず、死刑は刑罰として機能しておらず、このような者は、例外的なのかもしれないが、決してこの人間一人ではないとしています。
そこで、終身刑や無期懲役刑についても考えます。自分を死刑にしろ、という者にとっては、実はこの終身刑が最も苦痛であったわけであり、だから、(無期ではなく)真の意味での終身刑を以って最も重い刑とする案が生まれてくると。併せて、被害者遺族の応報感情についても考えます。著者は、死刑廃止論者が死刑廃止を望むならば、遺族たちの応報感情を満たすような代替案が必要で、ここでも、死刑より重い刑罰として終身刑が浮かび上がります。
さらに、犯罪抑止論の観点から死刑制度というものを考え、死刑制度によって犯罪が抑止できると言うより、その本質は、「最後は命によってつぐなう」という「道徳的歯止め」にあると。ただし、そうすると、「死ぬつもりなら何をしてもいい」という理屈になってしまい、そこで、「死ねば終わり」ではなく、「死ぬまで刑務所で罪を償わなければならない」終身刑が、ここでも浮上することになると。
第3章ではこれを受け、「人は人を殺してはいけない」という道徳について考えます。「なぜ人を殺してはいけないのか」についての道徳です。ここでは、まず「死刑は殺人か」、死刑制度の容認と「人を殺してはいけない」という道徳の関係を考えます(人工妊娠中絶はどうかなども考察)。そして、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いに対する幾つかの答えのパターンを示しますが、どれも決定的な答えになっていないと。例えば、「誰も他人の命を持っていないから」というのは「人を殺してはいけない」ということの同意置き換えにすぎず、「悲しむ人がいるから」は、そうした人がいなければ殺していいのかという反論に合ってしまう―根拠をつけようとすると反対に、その根拠がないと成立しないという制約を生んでしまい、やはり、道徳は相対的なものであるということです。
そこで、著者は、そうした考えに異を唱え、道徳は絶対的と考えたカントの「定言命法」を取り上げます。前節で述べた「悲しむ人がいるから人を殺してはいけない」といった論法は「仮言命法」であり、それに対し、「ダメなものはダメ」というのが定言命法です。根拠がないからこそ道徳は普遍的であるとうのがカントの考えです。言い換えれば、道徳は検証されなくとも力を持つということです。
カンㇳは死刑を肯定していますが、「人を殺しておきながら自分はのうのうと生きているなんて、どこに正義があるのか」という「同等性の原理」に依拠しています。そして、こうした同等性の原理に基づいて死刑を定めることを、1つの定言命法と考え、いかなる場合にも成り立つ普遍的な道徳と考えたと。ただし、定言命法ははあくまで原理であって、個々の道徳命題によっては表現されないとし、そうなると、定言命法は隠れた仮言命法でもあると言えると著者は言います。定言命法の根底にあるのは「他の人たちがしてもいいと思えることだけをしろ」という広い意味で応報論であると。
そこで著者は、根源的な道徳原理としての応報論と何かを考えます。そして、応報論は人間にとってもっとも親密な道徳原理であり、根源的な規範原理としての応報論は、「価値の天秤」で表されると。死刑賛成派と反対派の違いは、この価値観の天秤に何を乗せるのか、「殺人犯に奪われた命」と釣り合うのは、何を天秤に乗せるのかを巡る論争なのだとしています。
第4章では、死刑を政治哲学的に考えます。公権力が、死刑という暴力を実行できるのは何故か、というものです。いっそ国家というものがなかったら、という極論も世にはあるが、そうなるとそもそも刑罰どころの騒ぎではなくなるため、公権力が存在しない社会は考えられないと。ただ、ここで冤罪というものが問題の中心に置かれます。警察が冤罪を作ってきた背景や心理なども例を挙げながら示し、冤罪だけはなんとしても防がねばならないとしています。
再審で冤罪が明らかになった「足利事件」の例が出てきますが、すでに死刑が執行されている「飯塚事件」というのが紹介されていて、これが足利事件と同じく、当時のDNA鑑定に疑義ある事件であり、なんだかこれだけで1冊の本になりそうな話です(実際、『死刑執行された冤罪・飯塚事件』('22年/現代人文社)といった本になっている)。公権力の構造上冤罪は根絶できないことから、死刑を存置する理由は見当たらないというのが、著者の主張です。
第5章では、処罰感情と死刑についてです。死刑肯定論の根底には人々の強い処罰感情があるが、処罰感情には被害者や家族の気持ちが反映され、厳しい処罰はしたくないというケースもあると。処罰感情を寛容さで克服しようとするのが死刑廃止論だが、処罰感情は人間にとって根深いものであり、まず処罰感情を受け止めることから死刑廃止論は始まるとしています。
たいへん考えさせられる内容であり、これまでの自分の思惟がいかに情緒的なものであったかを思い知らされました。一方で、死刑制度に関して、処罰感情から検討を始め、死刑賛成論の根柢は応報論にあるとした上で、そこからさらに議論を深めるというよりは、相手の価値観を理解せよ、まず処罰感情を受け止めよ、といった具合に、また、処罰感情に帰結していく印象もありました。
結局、最後は、哲学的考察を深めると言うよりも、著者の"推し"は「死刑の代替としての終身刑」だということだったのかとの印象も。それでも、今まで死刑というものをこうした哲学的観点から考えてみたことがなかっただけに、自分自身の思索を深めることができ(たと思う?)、死刑論議の入門書として良かったです。
